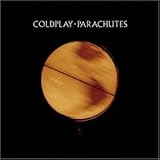“全米が泣いた”で泣けたためしがない
基本的に音楽は広く浅く聴くタイプなんだけど、十代の一時期、洋楽しか聴いてなかった頃がありました。
それも「ビルボード、何それ? 洋楽はやっぱUKでしょ」という痛い偏食ぶりで、マイナーどんとこい、むしろマニアックを極めるぜ、みたいな。
今で云う“中二病”ってやつですね。
同じ洗礼を受けてきた人には深く肯かれそう、ていうかニヤニヤされそうですが、当時の“神”はスミスとニュー・オーダーでした。
人によって太宰治なり尾崎豊なりに見出すものを、自分はスミスやニュー・オーダーに見ていたんでしょうね。
『デミアン』じゃないけど、青春時代って殻を破ろうとする葛藤のエネルギーが半端でなくすごいから、その捌け口として“神”が必要になるんじゃないかと思う。
換言すると、殻を破るための触媒というか導き手みたいな存在だろうか。
シンクレールにはデミアンがいたけれど、現実の若者がそんな人を得ることはまず無理なので、そこでスミスですよというわけですね、はい。
その後、青い春も無事過ぎ去り、スミスもニュー・オーダーもぱたりと聴かなくなって、淋しいけどもう卒業したんだわと思い込んでいたんですが――。
先日のこと、TSUTAYAで洋楽CDコーナーをぶらついてたら、最大級の賛辞を並べたかのようなPOPが目に入りました。
「現代で最も美しい音楽」とか「比類なき美しさと哀しみ」とかなんとか、そんな感じの。なんかやたら「美しい」を連発してた気がするな。ていうか自分で書いてて恥ずかしいよ、これ!
まあとりあえず、最近洋楽聴いてないし、なんか開拓したいなと思ってたところだったんで、釣られてみるかと借りてみたんですよ、コールドプレイを。
で、その結果が記事のタイトルだったと……。
うーん、美しいといえば美しいのかなあ……自分的には可もなく不可もなくというか、なんかこう“邪魔にならない音楽”って印象だったかな。
そう、邪魔にならないのが取り柄って感じ。
良くも悪くも灰汁がないんだよね。歌詞にしても英国バンドらしい暗さはあるんだけど、でも英国バンドならではの毒はない、という。
あ、そうか、だからアメリカでも売れたのかも。
世の中には、棘があるからこそ美しいものもあって、自分にとってそれこそが青春期に聴いた音楽だったんだろうな。
と、今更ながらに懐かしくなり、念の為に取っておいた昔のCDとカセット(!)を聴いてみたんです。
そしたらば。うは、全然卒業できてないじゃん、自分!ってことがよくわかりました。
いや真面目な話、聴き返して思ったんだけど、スミスもニュー・オーダーも純粋に楽曲としてすごくいいんですよね。
まあ、モリッシーの詞は今じゃあむしろギャグだけど、でもそれだってジョニー・マーのギターに乗るとこの上なく美しく聞こえるし。
三つ子の魂百までというか多感な頃の刷り込みも多少はあるにしろ、やっぱいいものは時代を超えて生き残るんだなあと思った。
そんなわけで、早速HMV(洋楽激安)に手放したCD注文しましたよ。今度は手放さないぜー!(たぶん)
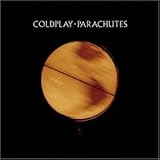
それも「ビルボード、何それ? 洋楽はやっぱUKでしょ」という痛い偏食ぶりで、マイナーどんとこい、むしろマニアックを極めるぜ、みたいな。
今で云う“中二病”ってやつですね。
同じ洗礼を受けてきた人には深く肯かれそう、ていうかニヤニヤされそうですが、当時の“神”はスミスとニュー・オーダーでした。
人によって太宰治なり尾崎豊なりに見出すものを、自分はスミスやニュー・オーダーに見ていたんでしょうね。
『デミアン』じゃないけど、青春時代って殻を破ろうとする葛藤のエネルギーが半端でなくすごいから、その捌け口として“神”が必要になるんじゃないかと思う。
換言すると、殻を破るための触媒というか導き手みたいな存在だろうか。
シンクレールにはデミアンがいたけれど、現実の若者がそんな人を得ることはまず無理なので、そこでスミスですよというわけですね、はい。
その後、青い春も無事過ぎ去り、スミスもニュー・オーダーもぱたりと聴かなくなって、淋しいけどもう卒業したんだわと思い込んでいたんですが――。
先日のこと、TSUTAYAで洋楽CDコーナーをぶらついてたら、最大級の賛辞を並べたかのようなPOPが目に入りました。
「現代で最も美しい音楽」とか「比類なき美しさと哀しみ」とかなんとか、そんな感じの。なんかやたら「美しい」を連発してた気がするな。ていうか自分で書いてて恥ずかしいよ、これ!
まあとりあえず、最近洋楽聴いてないし、なんか開拓したいなと思ってたところだったんで、釣られてみるかと借りてみたんですよ、コールドプレイを。
で、その結果が記事のタイトルだったと……。
うーん、美しいといえば美しいのかなあ……自分的には可もなく不可もなくというか、なんかこう“邪魔にならない音楽”って印象だったかな。
そう、邪魔にならないのが取り柄って感じ。
良くも悪くも灰汁がないんだよね。歌詞にしても英国バンドらしい暗さはあるんだけど、でも英国バンドならではの毒はない、という。
あ、そうか、だからアメリカでも売れたのかも。
世の中には、棘があるからこそ美しいものもあって、自分にとってそれこそが青春期に聴いた音楽だったんだろうな。
と、今更ながらに懐かしくなり、念の為に取っておいた昔のCDとカセット(!)を聴いてみたんです。
そしたらば。うは、全然卒業できてないじゃん、自分!ってことがよくわかりました。
いや真面目な話、聴き返して思ったんだけど、スミスもニュー・オーダーも純粋に楽曲としてすごくいいんですよね。
まあ、モリッシーの詞は今じゃあむしろギャグだけど、でもそれだってジョニー・マーのギターに乗るとこの上なく美しく聞こえるし。
三つ子の魂百までというか多感な頃の刷り込みも多少はあるにしろ、やっぱいいものは時代を超えて生き残るんだなあと思った。
そんなわけで、早速HMV(洋楽激安)に手放したCD注文しましたよ。今度は手放さないぜー!(たぶん)